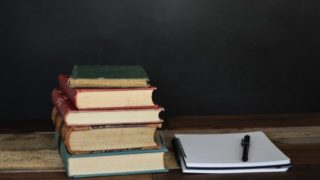はじめに
浴室や、洗面台の排水溝の縁に「赤い色」のものを見つけて、これは何だろうと思ったことはありませんか?
今回は赤カビの掃除と予防方法についてご紹介します。
見ただけで嫌な気持になる

筆者は自分で掃除をしますし、日頃から「掃除」にアンテナが立っています。
ですのでこの「赤い色」を見つけると、見ただけで嫌な気持になります。どういう嫌な気持かというと「あなた、掃除サボっているでしょ」と言われているような感じです。
また、どこかのお店の洗面所でこの「赤い色」を見つけると、「あっ、このお店あまり掃除していないな」と違う意味で嫌な気持になります。
赤カビの正体は?

赤カビの正体は何なのでしょうか?
酵母と言われている微生物で、菌類です。
家事代行の現場ではよく「ロドトルラ」と呼んでいます。
赤カビが発生しやすい環境は以下のとおりです。
(1)温度(20〜30度)
(2)皮脂や食べ物、汚れなどの栄養分
(3)湿度が高い
(3)の湿度が高いは、水分と(1)温度(20~30度)の条件があると「湿度」も高くなるということです。
赤カビの掃除方法

赤カビの掃除方法は、私の経験に基づいてご紹介します。「よくわからないな」と思う方は、他の掃除方法も調べてみて下さい。
浴室用洗剤で落とせる
赤カビは、浴室用洗剤とスポンジやブラシで簡単に落とすことができます。但し、以下の点に注意して下さい。
放置しない
赤カビは見つけたら、放置しないですぐに落として下さい。上で書いたとおり簡単に落とせるので、すぐに掃除してしまうのが一番良いです。
赤カビが発生するのは黒カビが発生する条件と同じです。
なので、そのまま赤カビを放置して掃除しないと、次に黒カビが発生してしまう可能性があります。すぐに掃除をしてしまうのが良いです。
予防が重要
赤カビは掃除で簡単に落とすことができます。
だから、掃除より「赤カビを発生させない予防の方が重要」です。
次は赤カビの予防についてご紹介します。
赤カビの予防方法

赤カビの予防方法をご紹介します。最初に私がどういう場面で「赤カビを見つけるのか」を体験を元にご紹介します。
湿度が高い環境
何と言っても「湿度が高い環境」で良く見るという実感があります。
見つけた時にその場所が「モワッ」とする湿気を感じる場所であることが多いです。
冬場の浴室で良く見る
家事代行の現場で体験してきたことから、冬場の浴室で良く見る印象があります。
「えっ、冬に!?」と意外に思うでしょうか?
たぶん、こういう事かなと予想できます。
寒いからお湯の温度を上げるため
冬は寒いので、シャワーや浴槽のお湯の温度を上げます。
その状態で浴室から出て、扉を閉めて、換気をしない。
そうすると、長い時間「モワッ」とした状態が続き、赤カビが生えやすい条件になっていると予想できます。
他には洗面台やキッチンシンクの排水溝で見ます
この2箇所でも良く見ます。排水溝で良く見るのは、湿気が高いのと、より汚れが多い場所だからかもしれません。汚れ=栄養分ですね。
予防は掃除と換気
基本はカビが発生しない様に対策するののと同じ方法になります。
発生条件の(2)温度はどうしようもありませんが、その他の2つは以下の方法で予防できます。
掃除
掃除をして、汚れ(=栄養分)が残らないようにします。
換気
換気をして、水分が残らない様にします。
風の流れも良くして、湿度が高くならないようにします。
赤カビは発生しない!
私の実感として、掃除と換気をして予防していれば、赤カビを見ることはありません。
さらに、「より予防」になる以下の2つの方法もご紹介します。
浴室から出る時に冷水をかけます
冬場の「モワッ」とした浴室の状態を防ぐために、浴室から出る時に全体に冷水をかけて温度を下げます。
但し、風邪を引かない様に注意して下さいね。
シャンプーや備品などをなるべく浴室に置かない
赤カビは浴室にあるシャンプーや備品などでも発生することがあります。
予防は浴室に置かないことです。
最初は「面倒臭いなー」と感じるかもしれませんが、浴室から出る時に毎回出して、洗面所などに置いておくのをオススメします。
慣れてしまうと、面倒に感じることもなくなりますよ。
まとめ
今回は、赤カビの掃除と予防方法についてご紹介しました。
掃除は簡単なので、予防をきちんと行って赤カビが発生しない様にして下さい。
赤カビが発生しなければ浴室を使っている時などに嫌な気持になることもなく、気持良く利用することができます。